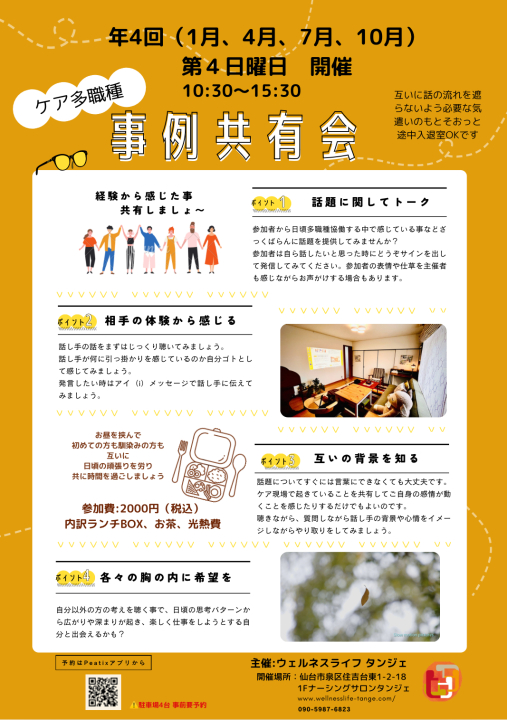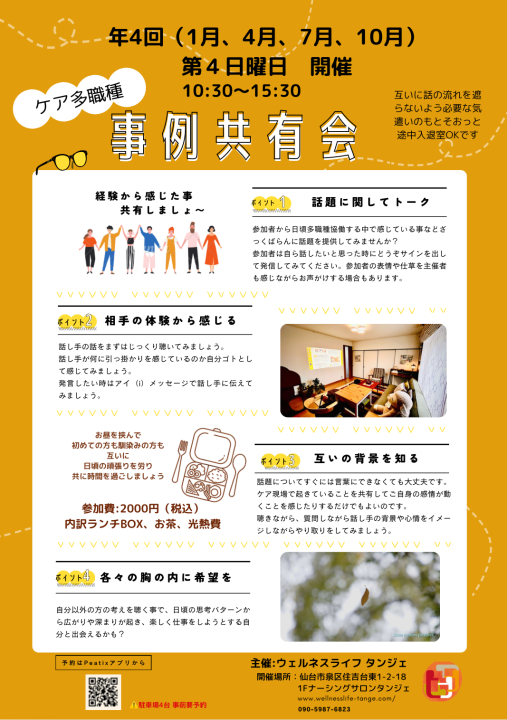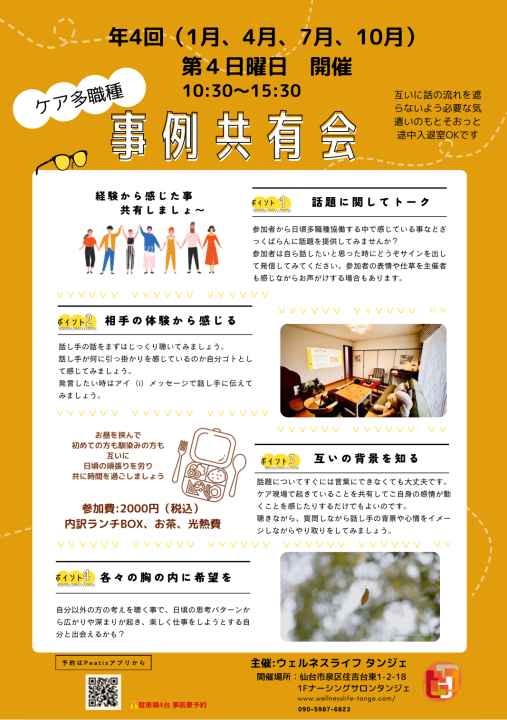2025年第2回【ケア多職種による事例共有会】
4月27日(日)10:30〜15:30 タンジェのナーシングサロンにて開催しました。
ご参加下さった皆さま、貴重な休日にお越し下さり誠にありがとうございました。
今回も初顔合わせがありましたが皆さまに『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視しながら参加頂けたこと感謝申し上げます。
今回も興味深い話題の提供を頂きました。提供頂いたテーマに大きくは「意思決定支援」がありました。対象者の方々との関わりを通じて看護師としてフットワークし、対象者にとって大変重要な今まで埋もれていたものを拾い上げながら労を惜しまずその先に繋げていく姿がありました。時には医療従事者との温度差に傷ついたり、進んでいる中この行動は本当に対象者の利益になるのか、といった不安や迷いを抱えながら。
事例共有会ではこのように一つの話題提供から、それにまつわる葛藤にも着目し、様々なテーマに展開します。
関係性へのむきあい、違いを認め、相手への敬意をはらうことに重きを置いた対話。「あなたが居てくれることが必要。あなたを私はこういう点で必要としている。」そんな対話の場をもつ勇気であったり、
時には精一杯やったけれどもまぁそんなに思うようにはいかないよね、という「まぁいいさ」という心のしなやかさも大事にしながら。
*今回もスローモーション・ピクチャーズ様の(https://sites.google.com/view/slowmotion-pictures/)ご協力を得て会場内に映像投影しながらの時を共に過ごしました。
次回は7月27日(日)に開催予定です。
お申込みはこちらから → https://tangewellness2025.peatix.com/
2025年第2回【ケア多職種による事例共有会】4/27(日)のお知らせ
2025年第2回【ケア多職種による事例共有会】
4月27日(日)10:30〜15:30 タンジェのナーシングサロン内にて開催
※参加費2,000円、ランチ飲み物付き
※最大5名までの小規模開催です
※お申込みは https://peatix.com/event/4312501
からお願いします。
ケアに携わる人たちのための職域や職場、立場を超えた語り場に来てみませんか?
ケアが、利用者さんが、患者さんが、仲間が好きだからこそ共有してみたいことありませんか?
初めての方も、参加したことのある方も気負わずざっくばらんにお話ししましょう。
お申込はコチラから。
※注:開催4日前までの事前申し込み、事前決済となっております。
*ご参加下さる皆さまへ*
「トークの前提となる方針とルールについて」のご案内
↓
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートします。
トーク時間は正味4時間とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
4月27日(日)10:30〜15:30 タンジェのナーシングサロン内にて開催
※参加費2,000円、ランチ飲み物付き
※最大5名までの小規模開催です
※お申込みは https://peatix.com/event/4312501
からお願いします。
ケアに携わる人たちのための職域や職場、立場を超えた語り場に来てみませんか?
ケアが、利用者さんが、患者さんが、仲間が好きだからこそ共有してみたいことありませんか?
初めての方も、参加したことのある方も気負わずざっくばらんにお話ししましょう。
お申込はコチラから。
※注:開催4日前までの事前申し込み、事前決済となっております。
*ご参加下さる皆さまへ*
「トークの前提となる方針とルールについて」のご案内
↓
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートします。
トーク時間は正味4時間とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
2025年第1回目の【ケア多職種による事例共有会】を1月26日(日)に開催しました。
2025年第1回目【ケア多職種による事例共有会】を開催しました。
貴重なお休みを使って参加下さった皆さまと今回もじっくりと語り合えたことを感謝申し上げます。今回は初参加の方もいらっしゃいました。
今回は一つの職場に長く就労している方と様々な場所で経験を積まれた方が混在した場になりましてショートストーリーが沢山語られた印象でした。
皆さん少し緊張しながらもざっくばらんな雰囲気のなかで十数年経った今だから、此処だから、この距離感だから語られたことがいくつかあったように感じております。
次回は4月の第4日曜日開催です。
職場や家や友人同士では語りきれない話、クローズドな場でしか話せない話、様々あるとおもいます。自身だけで抱えてきたけれども今なら話せるかも、と思ったことなど安心して話せる場です。どうぞお気軽にご参加くださいませ。
貴重なお休みを使って参加下さった皆さまと今回もじっくりと語り合えたことを感謝申し上げます。今回は初参加の方もいらっしゃいました。
今回は一つの職場に長く就労している方と様々な場所で経験を積まれた方が混在した場になりましてショートストーリーが沢山語られた印象でした。
皆さん少し緊張しながらもざっくばらんな雰囲気のなかで十数年経った今だから、此処だから、この距離感だから語られたことがいくつかあったように感じております。
次回は4月の第4日曜日開催です。
職場や家や友人同士では語りきれない話、クローズドな場でしか話せない話、様々あるとおもいます。自身だけで抱えてきたけれども今なら話せるかも、と思ったことなど安心して話せる場です。どうぞお気軽にご参加くださいませ。
2025年【ケア多職種による事例共有会】定期開催予定のお知らせ
2025年のケア多職種事例共有会は
1月. 4月. 7月. 10月の第4日曜
10:30~15:30開催 となりました。
◎該当月の事前のお知らせは2か月前から行います。
1月. 4月. 7月. 10月の第4日曜
10:30~15:30開催 となりました。
◎該当月の事前のお知らせは2か月前から行います。
第二回2024.11.9【ケア多職種による事例共有会】を開催しました。
第二回 2024.11.9【ケア多職種による事例共有会】を開催しました。
このたびも参加者の皆さまのご協力とご理解のおかげで無事開催することができました。
ありがとうございました。
ご参加頂いた方からメールを頂戴しました。
『すごく有意義な時間でした。ちょうど、わたしも、食形態のアレコレで色々と考える日々だったので、〇〇さんのお話に聞き入ってしまいました。
誰かの話をじっくり聞く、自分の話を否定せずに聞いてもらえる時間はとても貴重だと思いました。また、参加したいと思いました☺️
他にもいくつか聞きたいこともあったのですが、時間が足りず…今度、相談させていただけると嬉しいです。今日は、本当にありがとうございました✨』
このたびも参加者の皆さまのご協力とご理解のおかげで無事開催することができました。
ありがとうございました。
ご参加頂いた方からメールを頂戴しました。
『すごく有意義な時間でした。ちょうど、わたしも、食形態のアレコレで色々と考える日々だったので、〇〇さんのお話に聞き入ってしまいました。
誰かの話をじっくり聞く、自分の話を否定せずに聞いてもらえる時間はとても貴重だと思いました。また、参加したいと思いました☺️
他にもいくつか聞きたいこともあったのですが、時間が足りず…今度、相談させていただけると嬉しいです。今日は、本当にありがとうございました✨』
第二回【ケア多職種による事例共有会】11/9(土)のお知らせ
第二回【ケア多職種による事例共有会】
2024.11.9(土)10:30〜15:30 タンジェのナーシングサロン内にて開催
※参加費2,000円、ランチ飲み物付き
※最大6名までの小規模開催です
※お申込みは090-5987-6823へショートメールでお名前、連絡先、参加人数をお送りください
ケアに携わる人たちのための職域や職場、立場を超えた語り場に来てみませんか?
ケアが、利用者さんが、患者さんが、仲間が好きだからこそ共有してみたいことありませんか?
初めての方も、参加したことのある方も気負わずざっくばらんにお話ししましょう。
お申込はコチラから。
※注:開催5日前までの事前申し込み、事前決済となっております。
*ご参加下さる皆さまへ*
「トークの前提となる方針とルールについて」のご案内
↓
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートします。
トーク時間は正味4時間とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
2024.11.9(土)10:30〜15:30 タンジェのナーシングサロン内にて開催
※参加費2,000円、ランチ飲み物付き
※最大6名までの小規模開催です
※お申込みは090-5987-6823へショートメールでお名前、連絡先、参加人数をお送りください
ケアに携わる人たちのための職域や職場、立場を超えた語り場に来てみませんか?
ケアが、利用者さんが、患者さんが、仲間が好きだからこそ共有してみたいことありませんか?
初めての方も、参加したことのある方も気負わずざっくばらんにお話ししましょう。
お申込はコチラから。
※注:開催5日前までの事前申し込み、事前決済となっております。
*ご参加下さる皆さまへ*
「トークの前提となる方針とルールについて」のご案内
↓
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートします。
トーク時間は正味4時間とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
ケアに携わる多職種による事例共有会を終えて
2024.7.21(日)タンジェ(仙台市泉区住吉台)のナーシングサロン内にて
ケア職の方々にお集まり頂き【多職種による事例共有会】を行いました。
当日は30度を超える猛暑のなかでしたが参加者の皆さまにお集まり頂けたこと感謝申し上げます。初顔合わせの方々もありながらでしたが皆さん事前のルールのご案内のとおりどなたも理解的コミュニケーションをして下さりそれぞれの今の胸の内を飾ることなく語られていた印象がありました。
ご参加頂いた方々から会の終了後すぐにこんなお声を頂戴しましたので一部抜粋ではありますが掲載します。
ご参加下さった皆様が「また声かけて下さい!楽しみにしています!」とおっしゃって頂けたこととても励みになっております。
また秋ごろに企画しますので是非ご参加お待ちしております。
ケア職の方々にお集まり頂き【多職種による事例共有会】を行いました。
当日は30度を超える猛暑のなかでしたが参加者の皆さまにお集まり頂けたこと感謝申し上げます。初顔合わせの方々もありながらでしたが皆さん事前のルールのご案内のとおりどなたも理解的コミュニケーションをして下さりそれぞれの今の胸の内を飾ることなく語られていた印象がありました。
ご参加頂いた方々から会の終了後すぐにこんなお声を頂戴しましたので一部抜粋ではありますが掲載します。
- 数年前の自分はもがき苦しんでいたとふと思い出した場面もあって、今は分かち合える皆さんとこんな時間を過ごすことができるようになったんだなぁと、頑張ってきてよかったと改めて思うことができました。状況は変わらないけれども昨日までとは私の気持ちが違いますから不思議と明日からが楽しみです。
- 私だけじゃないんだ~と気持ちが軽くなりました。
- 同じような思いをされている方に力をもらい、明日からまたがんばってみようかなと思っています。
ご参加下さった皆様が「また声かけて下さい!楽しみにしています!」とおっしゃって頂けたこととても励みになっております。
また秋ごろに企画しますので是非ご参加お待ちしております。
7/21のイベントに参加の皆さまへ
この度はお忙しい中イベントに参加くださる事大変嬉しく、皆さまにお会いできることを感謝申し上げます。
皆さまの大切な時間や労力、お金を使って参加頂きますなかでお互いに今回のイベントに参加して楽しかったなぁ、とか少し充実した時間だったなぁ等なるべく心地良い時間だったと感じられるような共有会にしたいと思っております。
そこでイベント参加者同士で前提としたいことを事前にお伝えさせて頂きたく思います。
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
以上です。
今回は最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートしたいと思います。
トーク時間は正味4時間半とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
梅雨真っ只中ではありますが当日どうぞお気をつけてお運びくださいませ。
皆さまの大切な時間や労力、お金を使って参加頂きますなかでお互いに今回のイベントに参加して楽しかったなぁ、とか少し充実した時間だったなぁ等なるべく心地良い時間だったと感じられるような共有会にしたいと思っております。
そこでイベント参加者同士で前提としたいことを事前にお伝えさせて頂きたく思います。
【事例共有会の前提としたいこと】
一人一人が心理的に安全に
『話す』『聴く』『感じる』を主眼に置きたく思います。
そのために以下のことを一緒に大切にして頂ければ幸いです。
◉話の内容、人物その他個人や組織情報に関わることはできるだけ匿名性をもたせるよう配慮をお願いします。仮に特定できたとしてもこの場や共有した私たちの中だけのものとしておきたく存じます。
◉聴き手になる時は、固有の事例を提供してくれている話し手の気持ちを大切にし、話し手から『皆さんの忌憚のない意見や考えを聞かせてほしい』という語りかけがあった時以外は途中で意見を差しはさむことを避け、話しやすい雰囲気になりますよう理解的コミュニケーションと心配りをお願いします。
◉話し手は聴き手にどう考えますか?など質問したい場合もあるかと思います。話し手はお話をする時には聴き手が理解しやすいようできるだけ共通言語を用いたり補足説明をしたりするなどケア多職種が集っていることへの配慮をお願いします。
◉良いケアか悪いケアか、や正解か不正解かなどの物差し的な評価の場にしないように意識したいと考えています。互いに年齢や経験、立場などの影響を受けることなく肩の力を抜いて安心して話せる『場』を皆さんと創りたいと思っています。
◉事例共有の中で話の状況から自分以外の方の価値観や気持ちに触れることで自身の感情の沸き立ちに接することもあるかと思います。
そんな時、沈黙という時間が流れるとしても大丈夫です。何か話さなくちゃ、返さなくちゃと焦らず今のご自身の気持ちの動きなどを感じようとすることを大事にして頂きたいです。
以上です。
今回は最初にお名前とご職業をお伺いする程度にとどめてスタートしたいと思います。
トーク時間は正味4時間半とたっぷりありますが最初にどこの誰かということを詳細にインプットするより、『話し手の背景や心情、価値観をイメージしながら聴く』を重要視したいのでランチタイムの時にお互いの紹介は深く掘り下げて頂ければと思います。
梅雨真っ只中ではありますが当日どうぞお気をつけてお運びくださいませ。
ケアに携わる多職種による事例共有会のお知らせ
ケアに携わる多職種による事例共有会のお知らせ
【日程】2024.7.21(日)10:00~15:30
【場所】タンジェ(仙台市泉区住吉台)のナーシングサロン内にて
【対象者】ケアの現場で「何のためにがんばっているのか分からなくなったことのある方」ならどんな職種でも
【参加費】昼食お茶代込みで2000円
【駐車場】3~4台無料 事前申し込み
【公共交通機関によるアクセス方法】
地下鉄泉中央駅20番からバスあり。住吉台1丁目下車(21分乗車)徒歩1分
お帰りの際は毎時40分代に泉中央駅行きのバスあります。
泉中央駅近辺は有料駐車場沢山あり、最大700円前後。セルバ駐車場に停めて帰りに買物すると値引きが得られます。
企画主催)メッセンジャーナース(仙台)鳴海、松田
問合せ)090-5987-6823(鳴海)
【日程】2024.7.21(日)10:00~15:30
【場所】タンジェ(仙台市泉区住吉台)のナーシングサロン内にて
【対象者】ケアの現場で「何のためにがんばっているのか分からなくなったことのある方」ならどんな職種でも
【参加費】昼食お茶代込みで2000円
【駐車場】3~4台無料 事前申し込み
【公共交通機関によるアクセス方法】
地下鉄泉中央駅20番からバスあり。住吉台1丁目下車(21分乗車)徒歩1分
お帰りの際は毎時40分代に泉中央駅行きのバスあります。
泉中央駅近辺は有料駐車場沢山あり、最大700円前後。セルバ駐車場に停めて帰りに買物すると値引きが得られます。
企画主催)メッセンジャーナース(仙台)鳴海、松田
問合せ)090-5987-6823(鳴海)
第4回座談会8月27日(日)13:30~15:30を実施しました。
第四回座談会テーマ「在宅領域に従事する看護師の葛藤について」
ご参加下さった皆様お忙しい中ありがとうございました。
初参加の方が多く、互いにじっくり自己紹介しつつ今抱えている事柄や希望展望みたいなところにも思いを馳せながら時間が進みました。在宅領域は多様に富んだ職場背景も多く、一人一人が初めて知ることも多くその人が歩んできた世界を自分に照らしながら深く頷きながら聞き入っていらっしゃる参加者の姿が印象的でした。新たな繋がりができた場にもなり、自分は一人ではないかも、来てよかった、と感じて頂けた方も居たようです。
映像では、温かい看護と交流の実際を知り、「こんな看護がしたいと思って看護師になったんだったよね」という声も聞かれ、看護の原点を皆さんと感じることができたことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。
※今回は後半に社会福祉法人つどいの家「仙台つどいの家」様より毎年の実践報告イベント「すてーじ」からの映像「出会いを求めて」~彩也佳さんと角田さんの旅~
を鑑賞しました。(25分)
ご参加下さった皆様お忙しい中ありがとうございました。
初参加の方が多く、互いにじっくり自己紹介しつつ今抱えている事柄や希望展望みたいなところにも思いを馳せながら時間が進みました。在宅領域は多様に富んだ職場背景も多く、一人一人が初めて知ることも多くその人が歩んできた世界を自分に照らしながら深く頷きながら聞き入っていらっしゃる参加者の姿が印象的でした。新たな繋がりができた場にもなり、自分は一人ではないかも、来てよかった、と感じて頂けた方も居たようです。
映像では、温かい看護と交流の実際を知り、「こんな看護がしたいと思って看護師になったんだったよね」という声も聞かれ、看護の原点を皆さんと感じることができたことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。
※今回は後半に社会福祉法人つどいの家「仙台つどいの家」様より毎年の実践報告イベント「すてーじ」からの映像「出会いを求めて」~彩也佳さんと角田さんの旅~
を鑑賞しました。(25分)
7/2(sun) 勉強会「カフアシストの実際」を行いました。
医療的ケアを必要とする方などに排痰促進に活用されている機器「カフアシスト」をご存じですか?今回は講師をお招きして機器の使い方とその実際を体験を通して一緒に学びました。ご参加下さった方は介護職、看護職の皆さまでした。皆さんとても楽しそうに和気あいあいとして、聴きたいことを存分に質問できたと喜んでいらっしゃいました。ありがとうございました。
実際にカフアシストの機器フィリップスのE70を動かして、マスクを使って被験者(講師)に実施したり、自己実施しました。
生活リズムの中で、無理なく、誰もが、行えるスタイルでやっていくことを目標にすると生活の質が上がるということをお聞きし、そうだなぁ、人は暮らしがある、その中で体のコンディションを整えるためのちょっとした便利な道具として効果的に使えること、とても大切なことだと改めて感じました。
日時;2023.7.2(日) 14:00~15:30
場所:将監中央コミュニティセンター 第1会議室
講師:片山 望 氏(西多賀病院理学療法士)
実際にカフアシストの機器フィリップスのE70を動かして、マスクを使って被験者(講師)に実施したり、自己実施しました。
生活リズムの中で、無理なく、誰もが、行えるスタイルでやっていくことを目標にすると生活の質が上がるということをお聞きし、そうだなぁ、人は暮らしがある、その中で体のコンディションを整えるためのちょっとした便利な道具として効果的に使えること、とても大切なことだと改めて感じました。
日時;2023.7.2(日) 14:00~15:30
場所:将監中央コミュニティセンター 第1会議室
講師:片山 望 氏(西多賀病院理学療法士)

2023.4.23 第三回座談会 テーマ「福祉の場の看護師の役割について」を実施しました。
座談会当日は陽射しは暑く、でもサロンの中は暖房が少し必要という一日でした。状況に応じて参加頂いた看護師さんたちはマスクを外したり着けたりして想いを語って下さいました。ありがとうございました。
参加者の方々から頂いた感想を一部抜粋して掲載します。
「お給料が見合っていないと感じる中でも、利用者さん、患者さんを最優先に考えてそれをモチベーションにできて働き続けられる。大変で苦しい事の方が多い中なのに、続けられてしまう。その理由は好きだから、楽しいから、と仰る参加されていた〇〇さんから看護師になったことの意味を再確認させて頂きました。
自分には向いていると思っていた訪問看護から離れてしまうことになり、本意ではなかったと今でも考えます。様々な想いが行ったり来たりしている中、参加者の言葉を聴く度に癒されます。
自分は自分のままで看護師してていいんだ~失ったものを取り戻させて頂くような大変ありがたい機会を頂き感謝です。」
「今日は精神的に落ちていました。でも(座談会)皆さんとお話して今はちょっとまた頑張ろうと思えています。明日は分からないけど。。。」
以上
タンジェの座談会ではフラットに湧きおこった感情を共有しながらその場で吐き出せることを大事にしていきたいと考えております。そうすることで参加者が独りじゃないこと、ゆるやかなつながりの中で互いの存在がふとした時に支えになれたらいいなと思っております。
参加者の方々から頂いた感想を一部抜粋して掲載します。
「お給料が見合っていないと感じる中でも、利用者さん、患者さんを最優先に考えてそれをモチベーションにできて働き続けられる。大変で苦しい事の方が多い中なのに、続けられてしまう。その理由は好きだから、楽しいから、と仰る参加されていた〇〇さんから看護師になったことの意味を再確認させて頂きました。
自分には向いていると思っていた訪問看護から離れてしまうことになり、本意ではなかったと今でも考えます。様々な想いが行ったり来たりしている中、参加者の言葉を聴く度に癒されます。
自分は自分のままで看護師してていいんだ~失ったものを取り戻させて頂くような大変ありがたい機会を頂き感謝です。」
「今日は精神的に落ちていました。でも(座談会)皆さんとお話して今はちょっとまた頑張ろうと思えています。明日は分からないけど。。。」
以上
タンジェの座談会ではフラットに湧きおこった感情を共有しながらその場で吐き出せることを大事にしていきたいと考えております。そうすることで参加者が独りじゃないこと、ゆるやかなつながりの中で互いの存在がふとした時に支えになれたらいいなと思っております。
2023.1.29 第二回座談会 テーマ「福祉の場の看護師の役割について」を実施しました。
座談会当日はサロンのある住吉台は降雪後の真白な世界で、それでも雲の少ない晴れた日でした。足元の悪いなか貴重なお休みの日を使って遠路からご参加くださった参加者に感謝申し上げます。
ご参加下さった方が持参された資料にナイチンゲールの看護覚え書きにある「小管理」についてがありました。
ナイチンゲールは、自分がいなくても、誰もが同じ内容の看護ができるよう工夫することを「自分自身を拡大する技術」と説いているんですね。つまりチームワークが重要だと。この真理は福祉の現場で、障害者(受益者)の心身両面において健やかな日常を支えようとする看護師が普段から心に留めおく重要なキーワード。
どんなに良い日常生活の世話をしていても、小管理が欠けていればその結果は受益者にとって台無しになる。小管理というのは自分がそこにいないときも居る時と同様に行われるよう対処する方法を工夫し定着でき、受益者の益になる環境を作ることが重要だとナイチンゲールは説いているわけです。
所感ですが、これは特にここ数年未曾有のコロナ禍の事態にそれは強く浮彫りになったように思います。
看護師は育成段階で医療の世界で安全や衛生管理においても常に周囲は共通知識や認識のもと仕事をして来た背景があり、福祉の現場で多職種と目標にむかうとき様々な葛藤を抱えやすいですね。おそらくそこから解放されることは育成場所が医療の世界のみに重きを置かれている間はないと感じます。それだけ、人材の育成教育はその後に影響を強く及ぼすということなのだろうと思います。
詳細は省きますが日本では障害者への医療は見捨てられていた時代があり、今でも障害者にとって一般的な病院で入院生活を送ることはある意味命がけでもあります。そういった現実に直面しながら力を合わせて障害者の暮らしを心身両面から支えようとする看護の、看護師のあり方をこれからも考え続けていきたいですね。
座談を通して、何でも先回りして自分で全部やってしまうことなく、周囲の理解と共通認識や意義を感じてもらいながら看護師が居ない時も日常生活が送られること、そんなことを意識しながらやってみることも大事かな、なども含め多岐にわたり話が出来ました。
参加者より「今日は(座談会のあと)お花を買って帰ってきました。」と感想と共にご連絡がありました。
きっとお花を買うことで自分の命を感じ、心を癒し、色のある世界を実感なさりたかったのだろうと思います。その行動はまさにセルフケアの行動そのもの。
これからもタンジェのこもれびナーシングサロンでは座談会の催しを継続していきますのでご興味のある方は是非ご参加くださいね。
※次回は4月23日(日)13:30~15:30開催の予定です。
ご参加下さった方が持参された資料にナイチンゲールの看護覚え書きにある「小管理」についてがありました。
ナイチンゲールは、自分がいなくても、誰もが同じ内容の看護ができるよう工夫することを「自分自身を拡大する技術」と説いているんですね。つまりチームワークが重要だと。この真理は福祉の現場で、障害者(受益者)の心身両面において健やかな日常を支えようとする看護師が普段から心に留めおく重要なキーワード。
どんなに良い日常生活の世話をしていても、小管理が欠けていればその結果は受益者にとって台無しになる。小管理というのは自分がそこにいないときも居る時と同様に行われるよう対処する方法を工夫し定着でき、受益者の益になる環境を作ることが重要だとナイチンゲールは説いているわけです。
所感ですが、これは特にここ数年未曾有のコロナ禍の事態にそれは強く浮彫りになったように思います。
看護師は育成段階で医療の世界で安全や衛生管理においても常に周囲は共通知識や認識のもと仕事をして来た背景があり、福祉の現場で多職種と目標にむかうとき様々な葛藤を抱えやすいですね。おそらくそこから解放されることは育成場所が医療の世界のみに重きを置かれている間はないと感じます。それだけ、人材の育成教育はその後に影響を強く及ぼすということなのだろうと思います。
詳細は省きますが日本では障害者への医療は見捨てられていた時代があり、今でも障害者にとって一般的な病院で入院生活を送ることはある意味命がけでもあります。そういった現実に直面しながら力を合わせて障害者の暮らしを心身両面から支えようとする看護の、看護師のあり方をこれからも考え続けていきたいですね。
座談を通して、何でも先回りして自分で全部やってしまうことなく、周囲の理解と共通認識や意義を感じてもらいながら看護師が居ない時も日常生活が送られること、そんなことを意識しながらやってみることも大事かな、なども含め多岐にわたり話が出来ました。
参加者より「今日は(座談会のあと)お花を買って帰ってきました。」と感想と共にご連絡がありました。
きっとお花を買うことで自分の命を感じ、心を癒し、色のある世界を実感なさりたかったのだろうと思います。その行動はまさにセルフケアの行動そのもの。
これからもタンジェのこもれびナーシングサロンでは座談会の催しを継続していきますのでご興味のある方は是非ご参加くださいね。
※次回は4月23日(日)13:30~15:30開催の予定です。

2022.10.23 第一回座談会 看護師限定テーマ「障害福祉の現場での戸惑い」を実施しました。
少人数ということや知合いも混じっていたこともあってか各看護師さんは表面的な話に終始することもなく、リラックスした時間を過ごされていたように感じました。
主催した側からの所感にはなりますが、看護師のもつ背景(以下※を参照)ゆえの介護福祉の世界に身を置いた時の葛藤は大きいのだなぁということです。
看護師が葛藤することは決して悪いことではなく、深い思考を経て時にはより良き道への原動力になるのだろうなぁということが一つ。
看護師ほど浅く広く学んでいる職種はいないことを恐らく看護師自身もあまり真剣に考えたことはないと思いますが、改めて看護師が受けてきた教育のすばらしさや、社会から求められている役割を客観的に考え自らのなかに看護師として自分はそこで何を求められ、自分は何ができるのか、何がしたいのか、そして周りとの協調の課題といった事柄を考えることになると思いますので多様な環境に身を置けることは幸せなことでもあると思いました。
また、日々の仕事のなかで顧客へのアプローチを積み重ね、成果物を生んでいるということ、素晴らしいな、と感じました。
※看護師は、人間の誕生から死を迎えるまでの生老病死のプロセスで起きる心身の苦痛やその予防への看護援助技術や理論を学んでいる人。全科(栄養やリハビリや放射線、薬剤、臨床検査なども含みます)を浅く広く座学したり、実習場として「病院」や「在宅」、その他保育園や施設等で実習を重ねてようやく看護師になる。常に求められてきたのは予測、予防を含めたアセスメント力とケアの対応力。
主催した側からの所感にはなりますが、看護師のもつ背景(以下※を参照)ゆえの介護福祉の世界に身を置いた時の葛藤は大きいのだなぁということです。
看護師が葛藤することは決して悪いことではなく、深い思考を経て時にはより良き道への原動力になるのだろうなぁということが一つ。
看護師ほど浅く広く学んでいる職種はいないことを恐らく看護師自身もあまり真剣に考えたことはないと思いますが、改めて看護師が受けてきた教育のすばらしさや、社会から求められている役割を客観的に考え自らのなかに看護師として自分はそこで何を求められ、自分は何ができるのか、何がしたいのか、そして周りとの協調の課題といった事柄を考えることになると思いますので多様な環境に身を置けることは幸せなことでもあると思いました。
また、日々の仕事のなかで顧客へのアプローチを積み重ね、成果物を生んでいるということ、素晴らしいな、と感じました。
※看護師は、人間の誕生から死を迎えるまでの生老病死のプロセスで起きる心身の苦痛やその予防への看護援助技術や理論を学んでいる人。全科(栄養やリハビリや放射線、薬剤、臨床検査なども含みます)を浅く広く座学したり、実習場として「病院」や「在宅」、その他保育園や施設等で実習を重ねてようやく看護師になる。常に求められてきたのは予測、予防を含めたアセスメント力とケアの対応力。